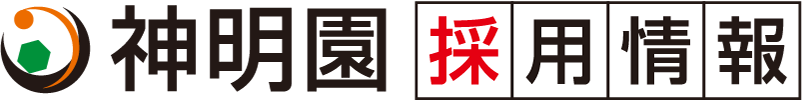見て、得て、感じて、考えて、それを繋ぐ
介護職になって3年目のある日、家族と疎遠になり施設で暮らすほぼ生活すべてに介護を要する笑わない男性のことで、ふと気になったことがあった。
入職して先輩たちから伝えられたその男性の食事状況は全介助。私は疑いもなく今まで介助していたが、手の動きを見ていて「パンなら自分で食べられるんじゃない?」と同僚に聞いたら、「食べられるよ」と。
「知っている?なのになぜ介助していたのか…」
それまで仕事を覚えることだけに懸命だった自分にとって、本来行うべき残存能力を活用する介護への意識を強く認識した瞬間だった。
後、彼への声掛けの頻度も増え、心なしか私の声掛けへの反応が他職員と違うようになったのを感じるようになっていった。少しして産休に入り彼と顔をあわせることがなくなったが、半年ほどして生まれた子どもを連れ職場へ出向いた。
「生まれたんですよ」と声をかけたとき、はじめて彼の笑顔を見た。
この笑顔は、私たちにとっては日常的なことに対する支援の必要を痛感させるに十分だった。
私は、誰にでも平等に介護を通じ接していきたいと思っているが、そこにある平等は時に個別性への障壁になる。
「なかなか難しい…」
答えがはっきりしないことを自問自答する。しかしこれも仕事のやりがいなんだと思える今日この頃である。